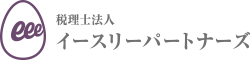税務調査で注目される「原価」と「在庫」のポイントとは?
税務調査が入った際、調査官が重点的にチェックするのが「売上」「原価」「在庫」の3点です。中でも「原価」と「在庫」は、企業の実態を反映しやすく、不正やミスが発覚しやすい領域です。本記事では、税務調査の観点から見たチェックポイントを詳しく解説します。
原価に関する税務調査の注目ポイント
原価は、売上と対応関係にあるため、売上が計上された事業年度に正しく計上されているかが調査の基本です。以下の点に問題があると、調査官は詳しい資料の提出を求めてくることがあります。
1. 原価構成要素の異常な変動
原価を構成する材料費・労務費・外注費・その他経費のバランスが前年と大きく異なる場合、あるいは業界平均から大きく乖離している場合は、調査対象になりやすいポイントです。コスト増減の理由が明確で説明できるよう、帳簿や契約書などの裏付け資料を整理しておきましょう。
2. 粗利益率の急激な変化
粗利益率は、不正の兆候が表れやすい非常に鋭敏な指標です。調査官はこの数字を重視しており、前年からの乖離が大きい場合には必ずヒアリングされます。安売りや大量仕入れ、特別な取引があった場合は、その根拠資料や取引内容を明示できるよう準備しておきましょう。
3. 販売費・一般管理費との区分誤り
原価として計上すべきものと、販売費や一般管理費に属する費用が混同されていると、所得金額が大きく変わってしまうため、調査官から厳しく指摘されます。仕訳基準や科目の使い分けルールを明確にしておくことが重要です。
4. 未着手原価の見落とし
年度末(特に3月)には、官公庁や大手企業からの「予算消化による押し込み発注」が行われることがあります。このような取引に対しては、請負会社が未着手でも見積もり計上が認められます。計上漏れがないよう、発注書・契約書の確認を徹底しましょう。
在庫に関する税務調査の注目ポイント
在庫は、期末における実地棚卸の内容が次期の期首に繋がるため、調査官が非常に注目するポイントです。わずかなズレでも複数期にわたって所得金額が変動するため、以下の点に特に注意してください。
1. 棚卸資産の過不足
期末の棚卸が正確に行われていない場合、翌期に繰り越される期首在庫にも影響を与え、結果として2期分の所得計算に誤りが生じる可能性があります。棚卸帳票と現物の整合性を事前にしっかり確認しておきましょう。
2. 粗利益率の変動と棚卸の関係
棚卸後に粗利益率が大きく変動している場合、調査官は「棚卸の誤り」「不正な計上」「売上除外」などを疑います。安売りや特別取引が要因である場合は、その経緯を明確に説明できるよう、売上伝票や社内稟議書などの記録を残しておくことが肝要です。
3. 商品の不正流出・盗難の可能性
以下のようなケースがあると、税務調査での問題発覚につながりやすくなります。
(1)商品の盗難・紛失
特に、化粧品・雑誌など、小売業で取り扱われる商品は盗難リスクが高く、利益に直結します。
(2)従業員・役員による横流し
過去の調査では、社員による不正流出が発覚するケースもあり、会社全体の管理体制が問われます。
これらを防ぐためにも、防犯カメラや在庫管理システムの導入、従業員教育の徹底が必要です。
税務調査に備えるための実務対応
-
日常的に「根拠資料を残す」習慣をつける
-
異常値(利益率、原価構成、棚卸金額など)は「その理由を記録する」
-
税務調査前には必ず「原価率」「粗利益率」「在庫帳簿と実物の突合」を行う
-
会計事務所や顧問税理士との定期的なチェックを怠らない
税務調査では、見た目の数字以上に「その裏にある実態」が重視されます。原価や在庫の管理は、適正な申告と健全な経営の基盤です。日頃から「説明責任を果たせる体制づくり」を意識し、トラブルを未然に防ぎましょう。
※本記事の内容は、掲載当時の法令・制度に基づいて記載しています。