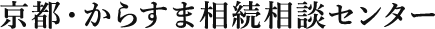買ったばかりの不動産がある場合の相続税
相続財産の中に相続発生直前に取得した不動産がある場合、評価で注意すべき点がいくつかあります。
1. 固定資産税評価額がついていない家屋
例えば、X1年6月に完成した家屋を取得しX1年9月に相続が発生した場合を考えます。固定資産税課税明細はX1年1月1日の所有者に届くため、この家屋は載っておらず固定資産税評価額がいくらか分かりません。建築中の家屋は「建築費用×進捗率×70%」で評価する通達があるため、「建築費用×70%(進捗率は100%)」で評価したらよいと考えがちですが、多くの場合固定資産税評価額よりも高く評価されてしまいます。一方、申告期限までに固定資産税評価額が決定した場合はその金額に基づいて評価してもよいとされています。今回の場合、申告期限がX2年7月に対して、X2年の固定資産税評価額がX2年4月には判明しているため、X2年の固定資産税評価額をもって申告すればよいことになります。
2. 貸付事業の用に供されていた宅地
多くの場合、小規模宅地等の特例(200㎡まで評価額を50%減額)を検討することになりますが、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地には適用できません(ただし、相続開始の3年前以前から事業的規模で貸付事業を行っていた場合は除く)。
3. 法人所有の不動産
被相続人が非上場株式を保有していた場合、株価を算定する必要があります。法人が所有する不動産は、個人で所有する場合と同様に財産評価基本通達に基づき評価しますが、相続開始前3年以内に取得した不動産は、例外的に通常の取引価額(時価)で評価することになります。家屋は減価償却後の簿価、宅地は取得価額と同額を時価とすることも少なくありませんが、いずれも通達に基づく評価額よりも大幅に高くなり、結果的に株価も高く評価される可能性が高くなります。
相続が近いからといって慌てて不動産を購入しても相続対策にならず、キャッシュが減って却って損したという結果になるケースも少なくありません。
また、こうした評価は税務調査で誤りやすい論点として指摘されやすいところです。
「不動産購入=相続対策」と短絡的に結論付けないことが必要です。