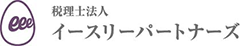開業時の社会保険
所得税や住民税の計算上、所得から控除できるものの1つとして「社会保険料控除」があります。これは自己または自己と生計を一にする親族の社会保険料(年金保険料や健康保険料)をその納税者(院長)が支払った場合は、その支払った金額を所得から控除できるというものです。そして、控除できる金額は、その年に実際に支払った金額もしくは給与や年金から天引きされた金額の全額となります。
ここでのポイントは、下記です。
1.原則としてその年に支払った金額の一部を翌年の控除にまわすことはできない。
2.いくら支払っても、そもそも所得がない場合(赤字の場合)は、何の効果もない。
なお、1の例外として、国民年金保険料は2年間分を一括払い(前納)できる制度がありますが、その場合「前納額全額をその支払った年の控除に入れる」と「その保険料に対応した各年それぞれの控除に入れる」とを選択することができます。
では、開業初年度について考えてみましょう。
開業月や医院状況にもよりますが、開業費用や設備投資が多いということもあり、開業初年度は赤字(所得なし)のケースはよくあります。その場合は上記2となりますので、仮に国民年金保険料を前納したところで何の効果もありません。そうであれば、支出の多い時期でもありますので、国民年金保険料は通常通り毎月支払い、利益(所得)が出るようになったら前納をするというのも1つです。
ただし、開業初年度で事業は赤字でも、前職やその他の給与があって、結果、所得がでる場合もありますので、そこの試算は必要です。
また健康保険料については前納といった制度はありませんが、「組合の国保」にするか「市の国保」にするかによって、保険料負担額が変わるケースがあります。
健康保険料については、前年の所得により当年度の保険料が決定しますので、例えば開業初年度の所得がゼロの場合の開業2年目の健康保険料は、組合の国保より市の国保の方が保険料負担は安くなる場合もあります。医師会や歯科医師会に加入している場合でも、医師組合国保や歯科医師組合国保を喪失して市の国保に加入することは可能のようですので、試算のうえ検討されてもいいのではないでしょうか。
開業したての頃は何かと資金が必要になりますので、こういう細かいところで出費をおさえるのも1つだと思います。